子どもの純粋な心を守る翼 - 幻の文芸誌『赤い鳥』第50号 日本文学史を彩る 1 冊
子どもの純粋な心を守る翼 - 幻の文芸誌『赤い鳥』第50号 日本文学史を彩る 1 冊
受取状況を読み込めませんでした
大空を舞う鷲 — 力強さと自由を象徴する表紙デザイン
「こちらをご覧になってください。この鷲の力強い姿、素晴らしいですよね。迫力があって、でも繊細さも感じます。」
手元の「赤い鳥」第50号を優しく開きながら、表紙に描かれた鷲の姿を指さす。褐色の羽毛の一枚一枚まで丁寧に描き込まれた繊細な筆致と、鋭い眼差しが印象的だ。

「この表紙を手がけたのは清水良雄という画家なんですよ。彼の描く動物たちは生命力に溢れていて、特にこの鷲の表現は見事だと思いませんか?」
赤と白のコントラストが鮮やかな表紙デザインは、大正から昭和初期にかけての「大正モダニズム」の影響を受けています。欧米のアール・デコやバウハウスの要素を取り入れながらも、日本独自の美意識で再解釈されているんですね。
「実はこの鷲には、単なるデザイン以上の意味が込められていたと言われているんです。高く飛翔する自由な精神を象徴していて、これは編集者の鈴木三重吉が掲げた『子供の純性を保全開発する』という理念を視覚的に表現しているんですよ。」
特にこの雑誌が発行された1935年頃は、日本が軍国主義化していく時代。そんな中で、自由に飛ぶ鳥のイメージには、文化や芸術の自由を守りたいという静かな抵抗の意味も込められていたのかもしれません。
「それにしても、この多色印刷の鮮やかさ。90年近く前の印刷技術とは思えないほど美しいですよね。この色彩の豊かさこそ、『一流の芸術を子どもたちに』という「赤い鳥」の精神そのものだと思うんです。」
子どもたちの心を育む宝庫 — 童話と童謡で彩られた文学空間
「この雑誌は、当時の子どもたちにとってどんな存在だったか想像できますか?今でいうYouTubeやゲームのような娯楽が限られていた時代、こんな美しい挿絵と質の高い文学に触れられることは、どれほど特別だったことでしょう。」
ページをめくると、井出八郎の手による繊細な挿絵が目に飛び込んでくる。建物や人物が生き生きと描かれ、物語の世界へと誘う。

「『赤い鳥』は家庭で親子が一緒に読むことを想定していたんですよ。特に人気だったのが童話と童謡欄でした。北原白秋、西條八十、野口雨情といった一流の詩人たちが童謡を寄せていて、その中には『からたちの花』のような今でも歌い継がれる名曲の原点があるんです。」
当時の教師たちも「赤い鳥」を授業で活用し、子どもたちに文学や音楽への興味を育むことを目指していたそう。単なる娯楽ではなく、教育的意義を持つ芸術作品として評価されていた。
「面白いのは、子どもたちも読者として参加できたことなんです。自分の書いた作文や詩、絵を投稿することができて、それが掲載されることが大きな喜びだったようです。今でいうSNSへの投稿のような感覚だったのかもしれませんね。」
さらにページをめくると、「少年少女」欄が見えてくる。そこには子どもたちの投稿作品が並んでいる。
「『赤い鳥』の読者たちは、兄弟姉妹や友人同士と互いに読者仲間を形成して、時には『赤い鳥』読者が集う『会』などに直接参加していたこともあったようです。今でいう同人誌即売会のようなコミュニティが形成されていたんですよ。面白いと思いませんか?」
芸術と教育の融合 — 先進的な印刷技術と一流の文学
「この雑誌の魅力は内容だけではないんです。触ってみてください、この紙質の良さ。そして細部に至るまで精緻な印刷技術。当時としては最高級の出版物だったんですよ。」
ページを光に透かしてみせる。上質な紙と鮮明な印刷が、90年近く経った今でも色褪せることなく残されている。

「『赤い鳥』の印刷にはリトグラフという石版印刷技術が用いられていました。これにより、細かい線やグラデーションを忠実に再現することができたんです。一般的な児童雑誌とは一線を画する仕上がりになっていますよね。」
同時代の大衆向け雑誌「少年倶楽部」などが安価で大量生産されていた一方で、「赤い鳥」は少部数ながらも高品質な製品として位置づけられていた。
「内容面でも一流でした。創刊号には芥川龍之介の『蜘蛛の糸』が掲載されていたんですよ。その後も有島武郎、泉鏡花、高浜虚子、徳田秋声といった一流文学者が寄稿していました。子ども向けだからといって手を抜かない、本物の文学を届けるという姿勢が徹底されていたんです。」
ページをゆっくりとめくりながら、挿絵と文章のバランスの良さを指し示す。
「この美しさと文学性の高さが、『赤い鳥』を他の児童雑誌と一線を画す存在にしていたんですね。それが今日、コレクター市場でも高い評価を受けている理由なんです。」
日本児童文学の原点 — 鈴木三重吉の理念と「赤い鳥」の誕生
「この雑誌の背景を少しお話ししましょうか。『赤い鳥』を創刊したのは鈴木三重吉という文学者です。彼は夏目漱石に師事した人物で、1918年、大正7年に『赤い鳥』を創刊しました。」
創刊当時の社会背景について語りながら、第50号の奥付を指さす。そこには「昭和十年二月一日発行」の文字が見える。

「創刊された1918年は、第一次世界大戦の終結期であり、日本では大正デモクラシーと呼ばれる民主主義的な風潮が高まっていた時代でした。教育界では明治期からの詰め込み教育や国家主義的な教育への反省から、子どもの個性や創造性を重視する自由教育運動が広がりを見せていたんです。」
三重吉の創刊理念について説明する。
「三重吉は当時の児童向け出版物を見て、『俗悪』で『下劣』なものが多いと感じていたそうです。そこで『世俗的な下卑た子供の読みものを排除して、子供の純性を保全開発するために、現代第一流の芸術家の真摯なる努力を集める』という理念を掲げたんですよ。」
創刊号は菊判、定価18銭と、当時としては高価な雑誌でしたが、評判を呼び、発行1万部のうち返品は1割に満たなかったと言われている。
「最盛期には発行部数が3万部を超え、『童話、童謡を入れること大流行』の時代がやってきたと三重吉自身が語っていたそうです。日本の児童文学史における転換点だったんですね。」
文化的遺産としての「赤い鳥」— その評価と現代的価値
「『赤い鳥』がなぜ今でもこれほど高く評価されているのか、それは単なるノスタルジーだけではないんです。この雑誌が日本の児童文化に与えた影響は計り知れないんですよ。」
そっと第50号を手に取り、表紙の鷲を再び眺める。

「『赤い鳥』に掲載された童謡は日本の音楽教育に大きな影響を与えました。今でも『童謡の日』として記念されているほどです。北原白秋は生涯に1,200編を超える童謡を残しましたが、その中でも『赤い鳥』に発表した300編以上の中に彼の代表作が多く含まれているんですよ。」
現代の児童文学への影響についても語る。
「『赤い鳥』で活躍した作家たち、特に芥川龍之介、北原白秋、新美南吉などの作品は、日本文学の重要な一部として今でも評価されています。これらの作家が『赤い鳥』に寄稿したことで、児童文学が単なる教育的な読み物から芸術性を持つ文学へと進化したんです。」
コレクター市場での価値についても触れる。
「コレクター市場では、『赤い鳥』は非常に高く評価されています。特に創刊号や終刊号、または表紙デザインが優れた号、例えばこの第50号などは希少性から高額で取引されることもあります。現在では1冊数万円から、状態の良いものだと数十万円で取引されることも珍しくありません。」
時代の中の「赤い鳥」— 軍国主義化する日本と文化的レジスタンス
「このお手元の第50号が発行された1935年、昭和10年頃の日本はどんな時代だったか想像できますか?」
当時の社会情勢について語りながら、雑誌の中身をさらに丁寧にめくっていく。

「この時期、日本は軍国主義化が進み、思想統制が強化されつつある時代でした。1931年の満州事変以降、日本は国際的に孤立を深め、国内では『国家主義』『皇国史観』が強調される風潮が強まっていたんです。」
そんな時代における「赤い鳥」の立ち位置を説明する。
「興味深いのは、この時期にも『赤い鳥』は創刊理念である『子供の純性を保全開発する』という姿勢を守り続けたことです。露骨な反体制的言動は避けつつも、子どもの純粋性や創造性を尊重する姿勢は、国家主義的・全体主義的な教育に対する静かな抵抗の意味を持っていたと言われています。」
挿絵のページを開き、そこに描かれた自由な表現に目を向ける。
「また、『赤い鳥』は国際的な視野も持ち続け、海外の童話や民話の翻訳・翻案を積極的に掲載していました。狭いナショナリズムに陥らない姿勢を貫いていたんですね。」
しかし、その翌年である1936年6月に三重吉が肺がんで亡くなり、「赤い鳥」は同年8月号をもって終刊したという悲しい結末も伝える。
「10月には360ページにおよぶ『鈴木三重吉追悼号』が出版され、18年にわたる『赤い鳥』の歴史に幕が下りました。短い期間でしたが、その影響は現代まで続いているんです。」
現代に蘇る「赤い鳥」— アンティークとしての楽しみ方と保存法
「では、この貴重な『赤い鳥』を現代において、どのように楽しむことができるでしょうか?いくつかご提案させてください。」
実際に雑誌を手に取りながら、様々な活用法を紹介していく。
「まず、教育的な活用法としては、お子さんやお孫さんと一緒に『赤い鳥』に掲載された童話や童謡を読み聞かせるのはいかがでしょう?90年近く前の作品でも、その普遍的な価値は色褪せていません。特に童謡は今でも歌い継がれているものが多いですよ。」
インテリアとしての活用法も提案する。
「また、このような芸術性の高い表紙デザインや挿絵は、額装して飾ることで素晴らしいインテリアになります。特にこの鷲のイラストは、モダンなインテリアにも和のテイストにも合いますよ。」
そして、コレクションとしての価値や楽しみ方について。
「コレクションとしても、『赤い鳥』は非常に奥が深いです。号数ごとに表紙デザインや内容が異なりますし、時代による変化も楽しめます。少しずつ集めていくのも面白いですよ。」
最後に保存方法についてアドバイスする。
「保管については、湿気や直射日光を避けることが重要です。中性紙の封筒や箱に入れて、温度変化の少ない場所で保存するのがベストです。また、防虫剤を使用して虫害から守ることも忘れないでください。」
第50号を大切に閉じながら、最後のメッセージを添える。

「『赤い鳥』は単なる古い雑誌ではなく、日本の文化遺産の一部なんです。これを大切に保存し、次の世代に伝えていくことは、私たち現代人の責任でもあるのかもしれませんね。どうですか、この鷲の表紙の力強さと、中身の繊細さの対比。素晴らしいと思いませんか?」
アイテムの基本情報
アイテムの基本情報
基本説明
雑誌「赤い鳥 第50号」です。中には、【ルミイ】【あたまでっかち】【子犬】などの童話や自由詩、俗話、綴方が書かれています。
サイズ情報
- 横:約15.5㎝
- 縦:約22.2㎝
- 厚み:約0.6㎝
カラー情報
- ホワイト
- ブラウン
- レッド
素材情報
- 本
アイテムの状態
アイテムの状態
タイプ
USED
コンディション情報
- 折れ・曲げなし
- 表紙・背表紙・裏表紙に汚れあり
その他情報
その他情報
共有する














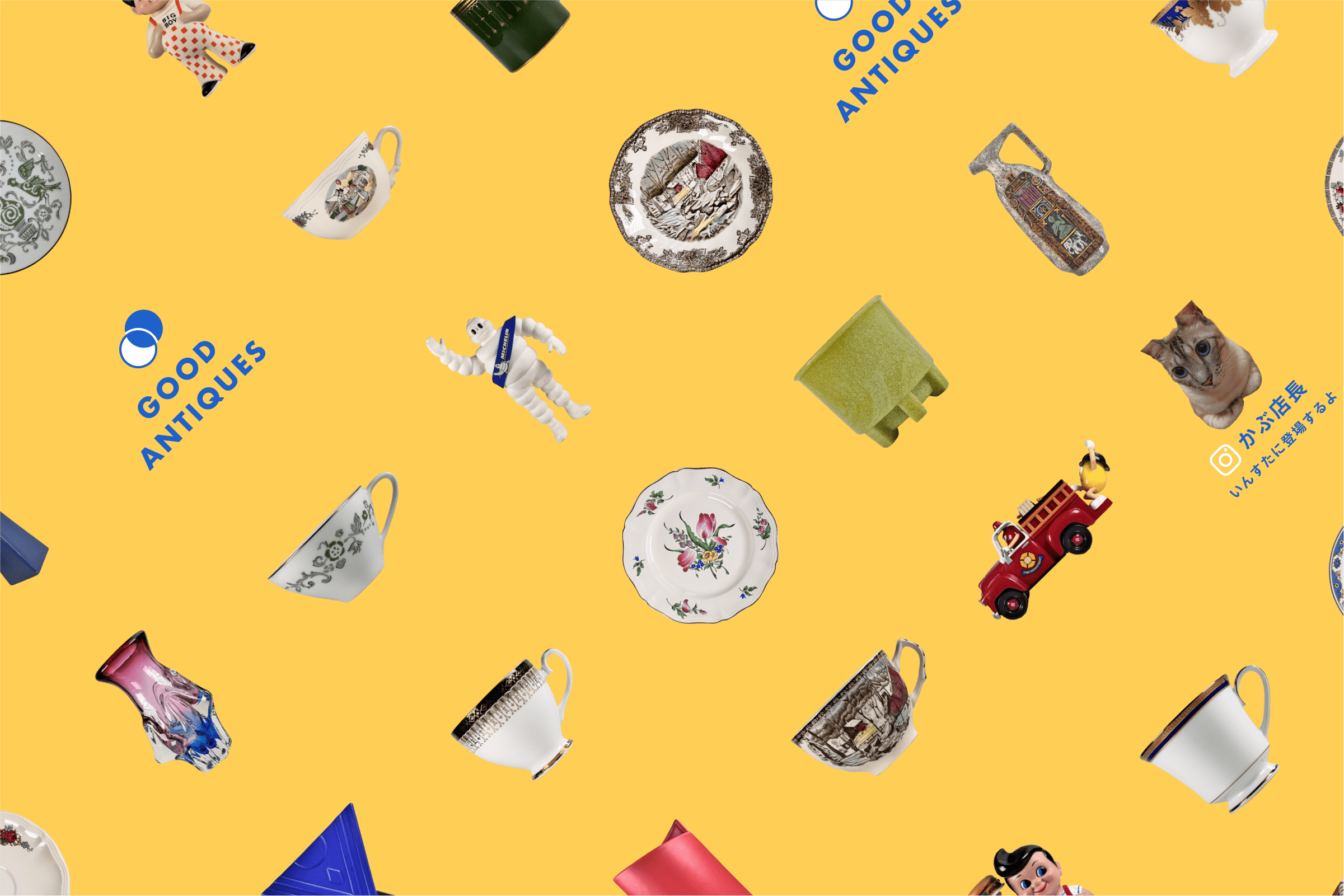
🗽 公式LINEに登録して 10%OFF クーポンをゲット!
公式LINEにご登録いただくと、商品代金から 10%OFF になるクーポンをゲットできます!その他にもおトクな情報やLINE公式限定の情報をお届けしておりますので、ぜひ、LINE 登録をしてみてください!













