夕陽の調べ 〜 昭和の職人が育んだ赤褐色の釉薬、和モダンな水差し
夕陽の調べ 〜 昭和の職人が育んだ赤褐色の釉薬、和モダンな水差し
受取状況を読み込めませんでした
炎のような釉薬が躍る、昭和の記憶を纏った水差し
「この水差しをご覧ください。深みのある赤褐色の釉薬が、まるで炎が踊っているかのように施されているんです。美しいでしょう?」
手に取ると、その艶やかな光沢が室内の光を柔らかく反射する。胴体には炎のような模様が浮かび上がり、それは昭和の職人たちの息遣いを今に伝えているかのよう。

「特に面白いのは、この釉薬の掛け方なんです。流し掛けという伝統技法を使っているのですが、それが和モダンの雰囲気を見事に表現しているんですよ。」
光の角度を変えながら、釉薬の深みある色合いを見せる。
「この曲線美にも注目してください。注ぎ口から持ち手まで、すべてが計算され尽くした優美さなんです。日本陶器さんならではの美意識が感じられますね。」
手元で慎重に回転させると、その曲線の流れるような美しさが際立つ。
「実は、この水差しには西洋のアール・ヌーヴォーの影響も垣間見えるんです。でも、それを日本の伝統的な技法で表現している。そこが魅力的なポイントですね。」
ふと、陽光が差し込んできて、釉薬の色合いがより一層深みを増す。
「このように光の加減で表情が変わるのも、高度な釉薬技術があってこそなんです。まさに昭和の技術の結晶と言えるかもしれません。」
暮らしに寄り添った、格調高き水差しの世界
「この水差しは、実は単なる水を注ぐための道具以上の存在だったんです。」
優雅な曲線を描く注ぎ口を指さしながら、

「お茶会では、このような上品な水差しを使うことで、場の格調を高める効果があったんですよ。注ぎ口の形状も、お茶を点てる際の水の量を絶妙にコントロールできるように設計されているんです。」
胴体のふくらみを優しく撫でるように触れながら、
「日常使いはもちろん、特別な席でも映えるように。そんな配慮が随所に見られるんです。例えば、この持ち手の角度。注ぐ際の安定感が抜群なんですよ。実際に持ってみていただけますか?」
水差しを慎重に手渡しながら、
「昭和期には、和と洋の文化が融合していく中で、このような多目的に使える道具が重宝されたんです。お酒を注ぐ徳利としても使えますし、お茶会での水差しとしても。」
「面白いのは、当時の人々の暮らしぶりが、このデザインに反映されているということ。例えば、この安定感のある台座。畳の上でも、テーブルの上でも安定するように考えられているんです。」
釉薬と形状が織りなす技術の粋
「この水差しの最大の魅力は、なんと言っても釉薬の技術にあるんです。」
光にかざしながら、釉薬の色の変化を示す。

「ご覧ください。この深みのある赤褐色。これは日本陶器さんが得意とした高温焼成による色合いなんです。実は、この色を出すのがとても難しいんですよ。」
胴体の模様を指でなぞりながら、
「この流れるような模様。職人さんが釉薬を流し掛けていく時の、微妙な手の動きが生み出す芸術なんです。一つとして同じ模様にはならない。そこも魅力的ですよね。」
「技術的な面で特筆すべきは、この均一な厚みなんです。ろくろ技術の高さを物語っているんですよ。触ってみていただけますか?」
実際に手に取っていただきながら、
「この滑らかな手触り。これこそが、工業化と職人技の見事な融合の証なんです。大量生産でありながら、一つ一つに魂が込められている。素晴らしいですよね。」
日本が誇る陶器メーカー、その歴史を紐解く
「日本陶器という会社、現在のノリタケの前身なんですが、実は明治時代の1904年に創業されているんです。」
古い写真を見るような仕草で、
「創業当時から、日本の伝統技術と近代化の融合を目指していたんですよ。この水差しにも、そんな理念が色濃く反映されています。」
水差しの台座を指さしながら、

「特に昭和期に入ってからは、輸出品として高い評価を受けていました。この安定感のある造形も、海外市場を意識してのことだったかもしれません。」
「面白いことに、1981年にノリタケに社名変更するまでの期間、日本陶器は日本の陶磁器産業の最前線で革新を続けていたんです。」
釉薬の色合いを見せながら、
「この赤褐色の釉薬なども、おそらく昭和30年代から40年代にかけて完成された技術なんですよ。当時の資料を見ると、新しい釉薬の開発に力を入れていた記録が残っているんです。」
文化と技術が織りなす価値の結晶
「この水差しが持つ価値は、単なる骨董品としての価値を超えているんです。」
慎重に水差しを回転させながら、

「というのも、これは昭和期の日本の文化的な転換点を象徴する作品でもあるんですよ。和と洋の美意識が見事に調和している。」
釉薬の模様を指さして、
「例えば、この釉薬の掛け方。伝統的な技法を基礎としながら、モダンな表現に昇華させている。これこそが、当時の日本陶器の革新性を物語っているんです。」
「実は、同じような水差しでも、これほど釉薬の効果が美しいものは珍しいんです。コレクターの間でも、この時期の日本陶器の作品は高い評価を受けているんですよ。」
光の加減で色合いが変化する様子を見せながら、
「特に、この色調の変化。これは高度な窯焼き技術があってこそ実現できるもの。職人技と工業技術の見事な調和を感じますね。」
時代を映す鏡としての水差し
「この水差しが作られたと推測される昭和中期ごろという時期は、日本の陶磁器産業にとって大きな転換期だったんです。」
懐かしむような表情で、
「当時、日本陶器は積極的に海外市場を開拓していました。この水差しのデザインにも、その影響が見て取れるんです。」
持ち手の造形を示しながら、

「例えば、この持ち手の形状。和洋どちらの使用法にも対応できるよう、細部まで考え抜かれているんです。」
「面白いのは、この時期の日本陶器が、伝統と革新のバランスを絶妙に保っていたこと。この水差しは、まさにその証なんです。」
釉薬の色合いを見せながら、
「この赤褐色という色選びも、実は当時のモダンデザインの影響を受けているんです。和のテイストを保ちながら、洋の要素を取り入れる。そんな妙技が感じられますね。」
現代に活きる、水差しの新たな魅力
「この水差しは、現代の暮らしの中でも素敵な存在感を放つんです。」
窓際に置いて光を透かすように、

「例えば、このように窓辺に置いて、一輪挿しとして使うのはいかがでしょう。釉薬の色合いが光を受けて、まるで宝石のような輝きを放つんですよ。」
「もちろん、本来の用途である水差しとしても素晴らしい。でも、それだけではもったいない。」
実際に使用例を示しながら、
「例えば、観葉植物のみずやりに使うのも素敵です。この注ぎ口の形状が、実は細目に鉢に水を注ぐのにも適しているんです。」
「保管方法も、実はとても大切なんです。湿度の低い場所で、直射日光を避けて保管することをお勧めします。」
丁寧に拭き取る仕草をしながら、
「お手入れは、柔らかい布で優しく拭くだけで十分。むしろ、過度な洗浄は釉薬を傷める可能性があるので避けた方が良いんです。」
「このように大切に扱えば、これからの100年も、美しい姿を保ち続けてくれると思います。素晴らしい逸品ですよね。」
アイテムの基本情報
アイテムの基本情報
基本説明
日本陶器の水差しだと推測されます。バックスタンプはありません。
サイズ情報
- 長径:約17㎝
- 短径:約13㎝
- 高さ:約26.5㎝
カラー情報
- ブラウン
素材情報
- 陶器
アイテムの状態
アイテムの状態
タイプ
USED
コンディション情報
- 大きな割れ、欠けなし
その他情報
その他情報
共有する








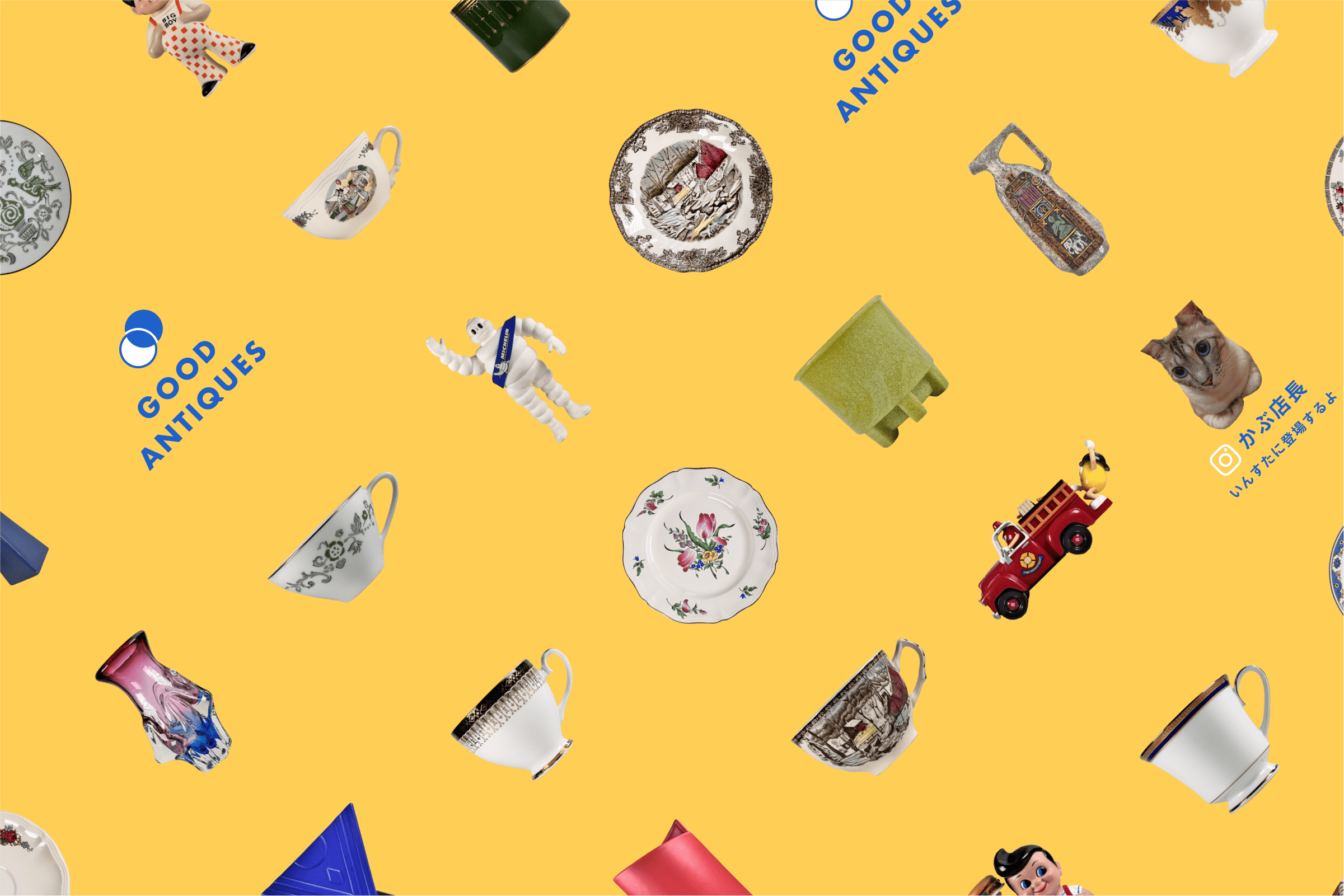
🗽 公式LINEに登録して 10%OFF クーポンをゲット!
公式LINEにご登録いただくと、商品代金から 10%OFF になるクーポンをゲットできます!その他にもおトクな情報やLINE公式限定の情報をお届けしておりますので、ぜひ、LINE 登録をしてみてください!







